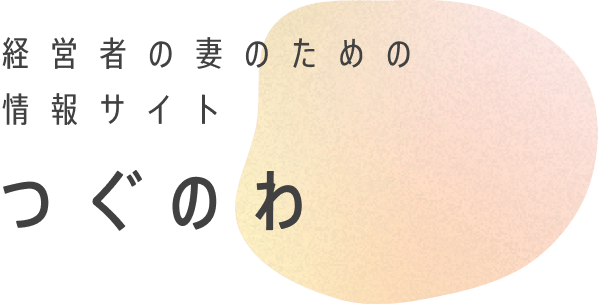夫の会社の成長を支える、経営者の妻の役割と心構えとは?
経営者の妻におすすめの賢い家計管理法
中小企業向け事業保険のエヌエヌ生命
経営者の妻の皆さまに向けて、賢い家計管理法についてお伝えしていきます。

経営者の妻におすすめの賢い家計管理法
今回は、経営者の妻の皆さまに向けて、賢い家計管理法についてお伝えしていきます。
経営者の夫の中には、優れた経営感覚を活かして家計管理もしっかりしてくれるという夫もいれば、会社の経営が忙しくて家計のことは妻任せという夫もいるかもしれません。
会社の経営と同じくらい、家計の管理も大切なことです。
この記事をきっかけに、家計管理について夫婦で改めて話し合う機会を持ってみてはいかがでしょうか?
1.家計管理の分担は?

一般的に、家計管理は夫婦のうちのどちらが担当しているケースが多いのでしょうか?
家計管理最終決定者と土地・家屋の購入の際の最終的な決定者に分けて、どのように分担している家庭が多いのかを、以下で見ていきましょう。
2.家計の管理方法

日本では、土地や建物などの金額の大きな買い物は夫主導や夫婦で相談して決定するけれど、家計の最終決定をするのは妻であるというパターンが多いように思われます。
共働きか専業主婦かなどによって、家事の分担には違いがあると考えられます。家事の分担がまだまだ妻の側に偏っている日本では、日常の家計管理は妻が担当する方が合理的な場合が多いと言えるのかもしれません。
とは言え、現実的には「細かいお金の管理は苦手」という方もいるでしょう。そういう場合には、金銭の管理が得意な方が担当すればよいのです。大切なのは、きちんと話し合って、意思の疎通を図ることです。一定期間ごとに見直しを一緒に行い、家計の状況は両者が常に把握しているのが理想的です。
具体的な家計の管理方法を、収入面から考えると、次のような方法が考えられます。
- 夫と妻の収入を全て合算して、その中から貯金と生活費を配分する
- 夫か妻のどちらかの収入で生活費を賄い、もう一方の収入は貯蓄にまわす
- それぞれの収入の中から生活費を分担して負担し、残りは各自が管理する
夫と妻の収入を全て合算する、もしくはどちらかの収入を生活費に充てるという場合には、夫か妻のどちらかが家計を管理して、お小遣い制にするというご家庭が多いのではないかと思います。
ですが、家計簿アプリを利用すれば、夫婦で共同して管理をすることも可能になります。
それぞれの家庭にとって最適な家計の管理方法をみつけることが大切です。
3.家計管理のポイント

家計を管理する上で大切なポイントを、以下にお伝えします。
これらを参考にして、賢い家計管理術を身に付けてみてはいかがでしょうか。
3-1.夫婦でしっかりお金に関する話し合いをする
家計管理のポイントとして、夫婦でしっかりお金に関する話し合いをすることが大切です。
「将来の目標のために節約したい」、「日々の生活にゆとりを持ちたい」など、夫婦で考え方が異なるとお互いにストレスになり、家計管理もうまくいかなくなります。
お互いの希望や考え方について理解を深め、納得して臨むことが必要と言えるでしょう。
3-2.長期的なライフプランを立て、それに合わせた資金計画を作る
長期的なライフプランを立てることで、ライフステージごとに必要な資金が把握できます。
子供の新入学時に必要となる学費、マイホームの購入のための資金、親や自分たちの老後に必要となる資金など、将来のどの時点でどれくらいの資金が必要になるかをあらかじめ把握しておくことで、資金計画は立てやすくなります。
3-3.長期的な資金計画に基づいて、月々の予算を決めて家計を管理する
長期的な資金計画を立てることで毎月必要な貯蓄額が把握できるので、その貯蓄を除いた範囲内で月々の予算を決めて家計を管理します。
その際には家計簿をつけて、お金の流れを見える化することが有効です。
細かく家計簿をつけるのが苦手という方や、忙しくて時間がないという方は、レシートをノートに貼り付けていくだけ、というような簡単な方法でも十分です。
3-4.家計簿アプリを利用する
無料で利用できる便利な家計簿アプリもたくさんありますので、それらを利用するのもおすすめです。
「家計簿をつけるのが苦手…。」という方も、自分に合った家計簿アプリを利用することで、楽しんで家計管理ができるかもしれません。
3-5.毎月の収支を夫婦でチェックする
月々の収支が予算通りおさまっているか、毎月の収支を夫婦でチェックすることも大切です。
一緒にチェックすることで、どちらかが頑張りすぎたり、一方が消極的だったりするというアンバランスを防ぐ効果が期待できるでしょう。
3-6.貯金口座を複数つくり、目的別に使い分ける
貯金口座を複数つくり、長期的な資金計画用の貯金と、1年以内に必要となる資金用の口座を使い分けると便利です。
例えば、固定資産税や住民税などの税金の支払いや、車検の費用、旅行のための費用などを別口座で管理していれば、口座にお金を入れておくのを忘れたり、うっかり使ってしまったりするというような心配がなくなります。
4.家計簿アプリの効果的な利用法

買い物の際の決済手段が多様化し、クレジットカードやスマートフォンなどのキャッシュレス決済を利用する人が増えてきました。
そういうケースでは、従来の紙による家計簿では管理が難しくなってきています。
キャッシュレス決済ではお金を使った感覚が薄いために、気づかずに使いすぎてしまうのではないかという心配もありますが、家計簿アプリを上手に利用することで、かえって管理が楽になることもあります。
そこでここでは、家計簿アプリの効果的な利用法について説明します。
4-1.家計簿アプリの使い方
家計簿アプリには、アプリ画面から収入や支出を入力すれば自動的に収支を計算してくれたり、カメラで撮影すればレシートの内容を読み取って自動的に家計簿を作成してくれたりするものもあります。
ですから、まめに家計簿をつけるのが苦手だったという人も、家計簿アプリを利用すれば、楽しみながら管理ができるようになるのではないでしょうか。
また、支払いが必要なサービスを家計簿アプリに登録しておくと、支払い期日を知らせてくれるので、支払日を管理していなくても支払い忘れる心配がなくなります。
さらに公共料金の支払いやスマホの料金などの引き落とし、日常生活での支払いをクレジットカードやスマホ決済などのキャッシュレス決済にして、家計簿アプリと紐づけておけば、支払いの状況が一目で分かるようになり、お金の動きを一括で管理できるのでとても便利です。
銀行の口座やクレジットカードだけではなく、ポイントカードも登録しておくと、ポイントの残高を管理できるアプリもあります。
ポイントの残高も手軽にチェックでき、使い忘れがなくなりそうです。
自分の所得や家族構成、居住地などを登録すると、最適な支出の割合まで表示してくれる機能までついているアプリを利用すれば、事前の予算管理の手間も省けるかもしれません。
ただし、アプリによって備えている機能には違いがありますので、自分が使いたいと思う機能を備えているアプリを探してみるとよいでしょう。
4-2.夫婦で家計簿アプリを共有してみては?
家計簿アプリを利用することで、夫婦で家計簿を共有することができるようになるのもメリットと言えます。
同じ家計簿アプリを共有して、お金の流れを一緒に管理できるようになれば、将来的な資金計画に向けての進捗率などもお互いに把握できるので、ライフプランの見直しなど、お金にまつわる大切な話がしやすくなるでしょう。
5.家計管理と計画的に貯蓄することの大切さ
ライフステージの段階によって、大きなお金が必要になるタイミングとお金の入ってくるタイミングとはズレが生じるものです。
ですから家計を管理して、計画的に貯蓄していくことが大切になります。
それでも予期せぬ事態が発生して、予定外の出費が生じることもあれば収入が途絶えることもあるものです。
予想外の事態に一時期戸惑うことがあっても、計画的に貯蓄していて経済的な余裕があれば、何とか乗り越えられる可能性が高まります。
家族の将来のもしも…という事態に備えて、しっかり家計を管理し、計画的に貯蓄しておくとよいでしょう。
※本記事に記載の情報は2025年04月08日現在のものとなり、将来変更となる可能性があります。